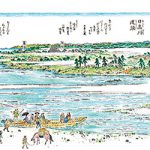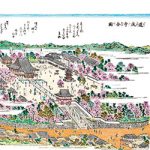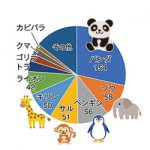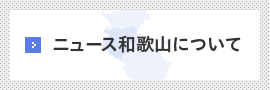夏休みと言えば昆虫採集というと少し昭和な感じかもしれません。先日、紀伊風土記の丘資料館が主催した「自然博物館マツノ学芸員と観る風土記の昆虫」に同行しました。夏休みに多様な虫がすむ里山で、子どもたちに虫捕りに親しんでもらう催しです。
集まった子ども、保護者は約30人。網に虫かご、帽子、水筒と装備はばっちり、やる気も十分です。猛暑のため時間を短縮しましたが、子どもたちはトンボやカマキリ、バッタ、コオロギを捕まえました。講師の松野茂富学芸員は不思議な飛び方をする虫をひとすくい。良好な水辺環境にすむチョウトンボでした。トンボにしては大きな羽にメタリックな光沢があり、その姿に驚きの声が上がりました。
私は、時間を追って子どもたちの動きが変わるのに感心しました。最初は闇雲に網を振り回していたのが、次第に虫の飛ぶ方向を読み、自分の気配を消して近づき、俊敏に網を振るようになります。誰に教わるわけでもなく、失敗、成功を繰り返し、自分で網さばきを磨いていくのです。
最近は、虫捕り少年、また虫自体の減少が懸念されています。ただ昆虫採集が育む力については論を待ちません。養老孟司さんらによる『虫捕る子だけが生き残る』(小学館)によると、虫捕りからは「気配を読む力」や「虫を手にする際に覚える力加減」「努力、根性、辛抱」まで身につく。また観察を通じ、自然の複雑さにふれ、現実は人間の思考で簡単に結論づくものではないと知る。生き物の命を奪う後ろめたさを感じるのも必要だと言います。何かを捕る積極性も含め、教室やバーチャル空間にないものがぎっしりあり、実際に私も野生とでも言いたくなる力が子どもの中にみなぎるのを目にした時はやはり感動しました。
催しの最後に松野学芸員が「虫を通じて自然や環境を考えてもらえれば」と話し、外来生物だけでなく、国内でもある場所で捕った虫を飼えないからと別の所に放すのをやめてほしいと訴えました。それだけ虫同士、植物とのかかわりは繊細なのです。環境の激変が肌で感じられる今、一匹の虫がそこにいる背景、その環境の来歴を含めて見つめる眼はよりリアルに未来を見通すと言えるでしょう。
養老さんは「ゾウムシ、コガネムシの区別もできず、十把一からげに虫と言う人はなんて野蛮なんだろうと思う」と言います(『大人になった虫とり少年』宮沢輝夫編、朝日出版)。私ももはや野蛮人の部類ですが、未来に向けて虫捕り少年の眼を取り戻したいです。(髙垣善信・本紙主筆)
(ニュース和歌山/2018年8月11日更新)