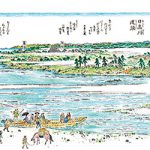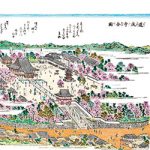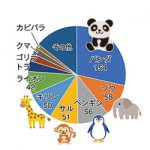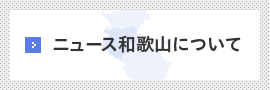『長い冬』は、アメリカの作家、ローラ・インガルス・ワイルダーが書き残した自伝的小説の一つです。ローラはテレビドラマ『大草原の小さな家』の原作者として有名です。開拓生活者の暮らしを描いた物語は人気で、今も再放送が繰り返されています。
日本で最初に翻訳されたローラの作品が『長い冬』で、1949年に発表されました。草原の町に猛吹雪が10月に訪れ、7ヵ月続いた吹雪の中での暮らしを描いた作品です。東部から食料や生活物資を運んで来る汽車は止まり、小さな町の人々はほとんど外出できず、主食の小麦、暖をとるものがなくなり、疲弊してゆきます。ローラの一家も食べ物が尽き、火にくべるものが絶え、馬の飼料の干し草を棒状にあんで、薪替わりにして寒さをしのぎます。先の見えない暮らしの中、時に皆で歌を歌い、父さんは子どもたちのために物語を語り、なんとか日を重ねていきます。
この最初の翻訳作は戦後、日本人に幅広く読まれました。多くの人が戦時中、物不足にあえぎ暮らしたことを重ねたと言われています。また2011年の東日本大震災の後もインターネット上で、被災地での暮らしと『長い冬』を重ねる声がありました。そして今、私たちは『長い冬』の中にいます。
なぜ、厳しい時期にこの物語が思い起こされるのでしょう。先の見えない中での、あるべきふるまいを教えてくれるからだと私は思います。
物語では、家族がいらいらし始めたり、小麦を隠し持ち売らない人が出てきたり、こんな時の人間の姿がリアルに描かれます。そんな中でも家族は、互いの声かけやちょっとしたふるまいといった小さなことで気持ちを変えます。
「けっして負けるものか」との父さんの言葉を「小さなともしび」に不便を乗り越えるのです。ローラがこの本の出版を機に日本人に寄せたメッセージにこうあります。「いつも一番いいことは、正直であること。自分に与えられているものを充分にいかせて使うこと、小さな日常のよろこびで幸福と感じること。苦しい時も元気にしていて危険な時に勇気を持つことです」
物語の最後で、汽車が町に訪れ、5ヵ月遅れてクリスマスの食べ物が届き、皆で祝います。私たちに届くのは1年遅れの五輪でしょうか。そうではなく、普通に触れ合え、出かけられるあたりまえの暮らしではないでしょうか。経済的苦境が懸念されますが、その有り難みを心の底から世界がかみしめる瞬間を、次につながる大切な経験にしたいものです。 (髙垣善信・ニュース和歌山主筆)
(ニュース和歌山/2020年4月4日更新)