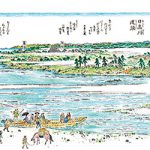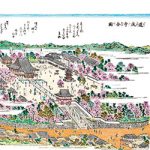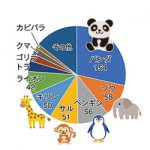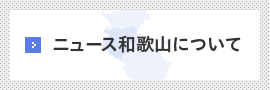第一楽章 おくゆかしき和歌山
2012年春、和歌山大学への着任を控えた私は、南海和歌山市駅前に降り立った。和歌山市について一定の予備知識を持ってはいたが、まちを歩きながら衝撃を受けた。
空き店舗や青空駐車場が目立つといった外見もさることながら、このまちには全く覇気がない。その後も出会う人には「こんなまち、何もあらへん」と言われ、散髪屋で東京から越してきたと言えば、なぜか同情される始末。
商業者や市民、行政にも漂う「あきらめ」の空気感。まちづくりの研究者としてご縁を得た土地とは言え、取り組みの糸口を見つけるのは容易でない。
一つの契機は、南海電鉄から観光学部への非公式的な依頼という形で訪れる。利用者が減り続ける市駅の将来像を一緒に検討したいという。再開発が具体化する前の話である。検討に加わった私は、提案をまとめてチームが解散した後も、市駅とまちの関係を掘り下げて理解するため、ゼミ生たちと歴史や現況を調べ始めた。
旧城下町の一角に開業し、百年以上もまちの発展を支えてきた市駅。一方で市民の間では「市駅は近々なくなる」という俗説も出回っていた。
そこで南海の協力のもと、市駅の歩みと存在価値を発信するパネル展を2014年3月に開催したところ、予想以上の反応を得た。8月には閉店前の髙島屋と合同で第2弾を開催し、この時はゼミ生たちとまちづくりの提案を考え、市街地模型とともに展示した。そこへ図らずも、雑賀衆の法被を着た市駅地区商店街連盟のM氏が現れる。
M氏は、しばらく展示を眺めた後、せっかくなので地元と一緒に議論しないかと声をかけてきた。まさに渡りに船である。
しかし地元が受け身になると意味がなく、商業者だけではまちは変わらない。考えた末、市駅周辺の商店街と自治会、私の研究室で「市駅まちづくり実行会議」を結成することを提案し、いよいよ実践が始まった。
(ニュース和歌山/2020年1月11日更新)